高齢化社会の砦【介護保険制度の仕組み】を解説します!

こんにちは、特別養護老人ホームの介護福祉士【@しまぞー】です。

介護歴10年以上の介護福祉士、介護サービス事業の経験は
- グループホーム
- 小規模多機能居宅介護
- 介護老人保健施設
- 特別養護老人ホーム
4種類経験しています。
私の介護の経験値は、恐らく他の職場の介護職員より、多くの施設・事業所を経験があるといえるでしょう。
本記事は全く介護の知識がない方でも理解できるような内容にしました。
ぜひ、介護の仕事を知って頂き、興味を持ってもらえれば幸いです。
また、みなさんの中で介護へ興味があるようでしたら、とても役立つような関連記事も紹介しています。
本記事をスマホのブックマークにしておくことをおすすめします。
介護保険制度の仕組み

我々が生業としている介護の介護保険制度は、1997年に国会で決められた介護保険法に基づいて2000年より施行された制度です。
利用者の負担は応能負担から応益負担へ
20年後、団塊の時代の子供のが高齢者になり30%を超えると言う試算
2025年問題、介護職員が38万人不足する
応能負担とは
介護保険制度前のシステムで、利用する際に家族に大きな金銭的負担がかからない。
収入に応じて支払う金額が変わるシステムです。収入が少ない世帯は支払う額が少なく、収入が多い世帯は多くの金額を支払います。
かつて、介護サービスは老人福祉制度と老人保健制度に基づいて行われていました。
老人福祉制度では「応能負担」が用いられ、世帯の収入によって支払う利用負担額が異なっていました。
応益負担とは
介護保険制度が始まると、「応益負担」が用いられるようになりました。「応益負担」とは、収入の差に変わりなく、皆が同じ金額を支払うというシステムです。
サービスを利用する人が利用額の1割(もしくは2割 2015年8月から)を負担するというシステムに変わりました。
介護保険制度における財源構成は、公費50%、我々が払っている介護保険料50%です。更に細かく説明すると・・・
公費の50%の内訳は国が25%、地方自治体が25%です。
今現在介護保険料50%の徴収年齢内訳(割合)は・・・
- 40歳から64歳が第二号被保険者・・ 32%、
- 65歳以上が第一号被保険者・・・・ 18%
と言われています。
そこで当然高齢化率は高くなるわけで
- 第二号被保険者の割合が減る
- 65歳以上の第一号被保険者の割合が高くなる
介護保険料は、現役で働いている40歳から65歳の第二号被保険者の給与・賞与が高ければ高いほど多く支払っています。
つまり第二号被保険者(40~64歳)の割合が減ると言うことは、介護保険料の徴収額が減少すると言うことです。
介護保険は徴収され何に使われるかと言うと、要支援、要介護者への介護サービス費です。
このままでは高齢化により第一号被保険者(65歳以上)が割合が増える。つまり、介護保険を利用するための財源が足りなくなっていくということです。
介護保険制度、介護サービス費の種類

介護保険サービスは、大きく分けて2種類に分けらえています。
- 居宅サービス(デイサービスや訪問サービス)なら区分支給限度額の利用金額
- 施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設)なら定額制の利用料金
簡単にいえば、居宅サービスは利用した分、施設サービスは定額料金といえます。
それぞれ一割が利用者負担と、その公費の9割を合わせた10割が介護保険サービスに使われています。
福祉サービスを提供する事業所、施設にには利用者に一割負担分の料金を請求、後の9割は国保連(これが保険者自治体です)に請求します。
国保連とは、保険者元の市町村です。
国民健康保険団体連合会 国民健康保険団体連合会とは、国民健康保険法の第83条に基づき、会員である保険者(市町村及び国保組合)が共同して、国保事業の目的を達成するために必要な事業を行うことを目的にして設立された公法人です。
居宅サービス費
居宅サービス費の区分支給限度額は要介護3なら26,750円が利用者負担分です。
施設や事業所は売り上げを立てるために、要介護3なら、MAXで26,750円が個人負担で使った分を請求する。
残りの9割が施設、事業所に9割負担分240,750円(もちろん利用者がサービスを利用した分の9割です)が国保連に請求します。
この居宅サービス費で間違いやすいのは、この金額は限度額で有って、実際に使った分が請求されます。
※例えば訪問サービスで一回身体介助を30分利用したら245円/一回です。
厚生労働省の区分支給限度額はこちらからどうぞ!
施設サービス費
施設サービス費は一か月の利用料金が、要介護3で23,280円です。
この金額が定額で利用者負担分として請求されます。
残りの9割209,520円を国保連に請求する事によって合計232,800円/1カ月が施設の売り上げとして立つのです。
特別養護老人ホームは施設サービスになりますが、介護度が3ならば、10割232,800円の売り上げ、プラス居住費、食費を徴収しています。
話はそれましたが、介護保険制度を踏まえたうえで、超超高齢化社会では第二号被保険者の割合は減り、介護保険の収入が減る。当然国の予算も収入が減る為、公費の介護保険料も悲鳴を上げてしまいます。
介護事業所、施設が商売としての売り上げが伸ばせないなら、給与はなかなか上げられない、高齢化社会で介護が有望なんて「大間違いです」と言う話です。
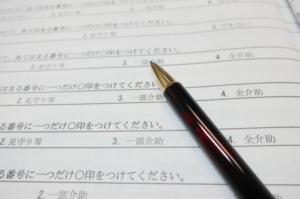
介護保険制度の将来

ちなみに私の考えで、介護保険制度を守るため国は、なるべく借金を増やさないための施策として
- 介護保険料の徴収は40歳からですがどんどん下げて年金同様20歳から徴収に引き下げられる。
- 介護保険料の金額が上がる。実際介護保険料の徴収金額は上がっています。しかしこれも限界があるでしょう。
- 介護保険利用者の負担率を1割、2割、3割とどんどん上げていく。
※今現在も収入により、3割負担の仕組みがすでに出来ています。

今日はブログを読んでいただきありがとうございます。また宜しくお願いします。
良かったらスマホにブックマークしてください。とても励みになります。
今日のサービスショット!
