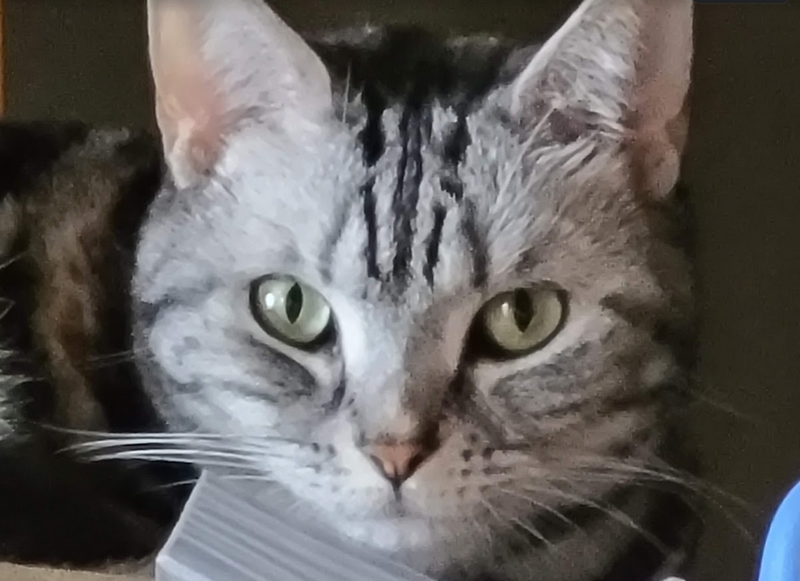介護の仕事に辛くなった時に読んでほしい!認知症利用者の拒否への対応の巻
【2021年10月9日更新】
こんにちは、特別養護老人ホームの介護福祉士【しまぞー】です。
今回は認知症の利用者の問題行動に悩んでいる方に向けて、私の経験をもとに記事にしました。
内容としては私の今まで8年間の介護経験の中で、認知症の問題行動になやみどのように解決してきたのか紹介したいと思います。
認知症利用者の拒否への対応で辛かった経験談

①:認知症利用者の入浴拒否が辛かった話
介護施設は認知症の入居者がほとんどです。若い方、介護に転職されてきた中高年の方の中には認知症の利用者に初めて接した方も多いと思います。
実際に体験すると拒否反応、徘徊、異食、弄便、etcなどの行動によりショックを受けることも多いでしょう。
かく言う私も最初に入職したグループホームでは、散々な目に合いました。これらの認知症の症状からくる問題行動にとても悩まされました。
私の体験談ですが、ある認知症女性利用者に悩まされたのです。そのグループループホームでは正社員の介護職員が5人でした。
女性利用者(A)様は入職した当時の私には優しく頬笑んでくれる方でしたが、しかし私は女性入居者(A)様に、一歩引いて接していたのです。
なぜかというと、その当時は認知症などの対応は初めてだったからだと思います。そしてその女性入居者(A)様の微笑みの中に何か違和感を覚えていたのです。
この一歩引いた利用者との接し方が、私が後々利用者の拒否反応により大変な目に合った原因です。
そうこうしてるうちに私は入浴介助を任されましたが、その女性入居者(A)様には入浴拒否をされたのです。確かに入居者(A)さんは入浴が嫌いだったのです。
しかし他の職員は、女性入居者(A)様を何とか入浴させていました。正確には私とユニットリーダーの女性が入れられず、他の3名の男性介護職員は入浴介助の拒否をされながらも上手く入れることが出来ていました。
この入居者(A)様の入浴拒否は、私がそのグループホームを退社する2年間続きました。
今思うと、今の私なら間違いなく解決できる問題だと思います。むしろそのような目に合う前に問題とならないように対策はしているはずです。
✔ 利用者の拒否行動をどの様に乗り越えたのかは、下にある「認知症利用者の拒否の対応の具体例」をご覧ください。
②:認知症利用者に入れ歯が入れずらくて辛かった話
入れ歯を入れずらい拒否される、この様な方も認知症の利用者に多数います。意外とベテラン職員でも、あきらめてしまう職員も多いと思います。
しかし入れ歯を入れっぱなしは衛生上よくないです。最悪誤嚥性肺炎の危険性が高まります。
私の体験談ですが、総入れ歯を入れる利用者(B)様がいました。とても入れ歯を入れずらい方だったのです。
私が入れ歯を入れて、その後口腔ケアの介助をしていた看護師から「唇に傷がついている」と言われました。
よく見ると2㎜ほどの線がうっすらと唇についていました。この件に関しては、特に愚痴とかではなくその看護師とは仲が悪い間だったのが話の前提にはあります。
実際数時間後確認するとその線も消えていました。
この件に関して何が言いたいかというと、私は入れ歯の入れ方をいろんな方に教わりました。解からないことがあったら、周りの職員に聞いてみるのが解決の近道だと思います。これをしない介護職員が多いのです。
これが”知識を得てスキルを身に付ける”という事です。周りの職員が先輩ばかりなら一時の恥を忍んで聞いてみようです。
せっかくなので、私の経験で入れ歯の入れ方を教わった職員の印象的な入れ方を紹介します。完全認知症の方が対象ですが、
とても役に立つ方法は、教えていただいた方からは「あまり無理に入れない」と言われました。
その方の入れ歯の入れ方は、片方の人差し指で唇の先を、横に思いっきり引っ張り広げるやり方です。「無理をしない?」とは思うが、これは結構難しい方でも出来ます。
もう一つは入れ歯の入れ方です。唇の先と入れば先を合わせて、斜めに入れるのがやりやすいと思います。
この場面もそうですが、「介助の基本はお声がけ」です。入れ歯を入れる際には必ず「〇〇さん入れ歯を入れますよ」とお声がけをすると自然とお口を開ける準備ができ入れやすくなります。
ちなみに後日談ですが、数年後の別の施設で歯医者に聞きました。
「総入れ歯で口に傷がつくのですか?」と、その歯科医ははっきり言いました。
「ありえません、あるなら入れ歯自体に傷がついている場合です。私は入れ歯の専門ですから」と、ホントくそ看護師でした。
③:夜勤で転倒リスクのある認知症利用者が徘徊するのが辛い話
私が今解決したいと思っているケースです。夜中に起き出すと手が付けられないです。
サークル歩行器を要ししていますが、なかなか促さないと使用しません。
転倒リスクがあるから日中も居室で臥床させているのです。夜中に起き出すと「お休みください」と言っても無理なのです。
ここから重要なのはチームワークです。日中帯で起きていただき、夜間や休んでいただく人間らしい生活が必要です。
利用者には「ストレスを与えない」、施設の生活に「安心感を与える」ことに尽きると私は思います。
認知症利用者の拒否の対応具体例
認知症対応でどのような解決方法かというと、これはもう「当たり前でしょう」と思われるかもしれませんが、「傾聴し笑顔とコミュニケーション」をとり続けるのです。
この繰り返しです。食事介助や入浴介助中、トイレ誘導のトイレの中でもです。
このサイトはとても教科書として勉強になったので紹介します。↓
内容を抜粋し引用すると
認知症は、記憶などの知的機能が衰えても、感情の機能は衰えていません。どうして叱られているのかはわからないけれど、叱られていることだけは理解しています。
もしも、あなたがわけもわからず急に大声で怒鳴られたらどうでしょうか。嫌な気持ちになりませんか?それと同じことです。そして、何について怒られたかという記憶は忘れても、不快な気持ちにさせられたことは覚えています。
このような嫌な気持ちが蓄積してしまうと、行動異常や妄想などが悪化し悪循環に陥ってしまいます。
✔ この考え方を私なりの言葉で解釈すると・・・
認知症の方の多くは、心の奥底で分かっています。大げさに言うと、心の中では接してくる職員を、敵か味方か判断しています。
良いのです、認知症で意思疎通が取れない方でも私はしゃべくり続けます。そうすると認知症の方は、私の事を味方だと思い拒否が少なくなりました。
もちろん認知症の方にはいろいろな症状があります。「ひとくくりにするのはどうかな?」とも思われるでしょう。しかし認知症に関わっていると大体3.4パターンに分けることができるようになります。
基本としてはどのパターンでも笑顔とコミュニケーションで対応します。ただそこから自分の持ち球を増やし、変化球を加えて試行錯誤し解決できるようになる。 そうすると更に認知症に対する対応力が身に付きます。
要は問題があればあきらめずチャレンジしていってください。そこで問題がクリアーしていけば自信になり、楽しみながらスキルがアップしていきます。
現在介護歴8年目ですが、前の様に拒否されることはほとんどありません。
苦手と思ったら、ある時は押したりある時は引いたりの繰り返しです。
更に「いいケアネット」さんの記事を引用します。
認知症の方にストレスを与えたり、放置したりするのもNGです。
ストレスがたまってしまうと、大きな声を出したり、暴力的になったりと、不満が表面化します。
無視したり放置したりすることも良くありません。孤独を感じることでもストレスが生まれます。
「ストレスを与える」「放置する」もNG
✅ 介護での離職理由第一位、人間関係の記事を5本用意しました。
良かったらどうぞ!
今日はブログを読んでいただきありがとうございます。また宜しくお願いします。
良かったら読者登録・Bマークしてください。とても励みになります。
今日のサービスショット!